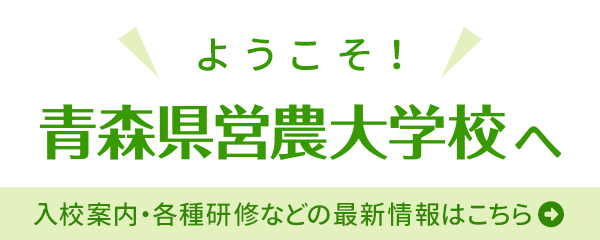青森県では、(公社)あおもり農業支援センターや各地域県民局地域農林水産部、各市町村等において、随時就農に向けた相談対応や情報提供を行っています。
相談をする際には、あらかじめ自分が目指す農業のイメージを頭の中に描いておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。
実際に農作業を体験したり、先輩農家から話を聞いて、農業が自分に合っているかを確認しておくことも大切です。
1.就農相談
就農する地域が決まっていない方、幅広く情報収集したい方
公益社団法人あおもり農業支援センター
| 対応時間 | 月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)9:00~17:00 |
|---|---|
| 場所 | 〒030-0801 青森市新町2-4-1 県共同ビル6階 |
| 電話番号 | 017-773-3131 |
※事前にお電話等で御予約いただくとスムーズです。また、リモート相談も可能です。
就農する地域が決まっている方
県内6か所に設置している地域県民局地域農林水産部や各市町村などで随時対応をしています。
相談窓口一覧
2.農業体験
農業法人が実施するインターンシップ(短期就業体験)のほか、市町村等が実施するイベントもあります。
インターンシップ
仕事として農業に興味がある方が、実際に農業の現場で短期就業体験できる制度です。インターンシップを受入れている農業法人の情報は「雇用就農ガイドブック」からも確認できます。
雇用就農
3.就農を支援する組織
①市町村
各市町村の農業関係課で新規就農者の支援に取り組んでおり、認定新規就農者制度や国等の事業を活用する場合の窓口も市町村となります。
また、市町村によっては、独自の新規就農支援策を実施している場合があります。
市町村の支援制度
②農業委員会
市町村役場の中に農業委員会があります。農業委員会では、農地法の許認可などの仕事に加えて、本気で農業をしようとする人へ農地をあっせんするなど、地域の農業生産の担い手を育てることにも力を入れています。
新規就農を希望する人が農地を取得するには、最終的には農業委員会に行き、手続きをする必要がありますので、あらかじめ相談することをお勧めします。
③公益社団法人あおもり農業支援センター
公益社団法人あおもり農業支援センターは、新たに就農しようという方への支援や担い手農業者への農用地の利用集積、畜産関係の施設整備等を行っている公益法人です。
新規就農者に対する支援策の一つである、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付主体となっています。
また、無料職業紹介所として農業法人等の求人紹介、各市町村の地域担い手育成総合支援協議会と連携して就農関連情報の提供や就農相談活動を実施しているほか、農地中間管理機構として、農地の貸借や売買に関する農業者への支援も、各市町村の農業委員会と協力して行っています。
④農林水産事務所
県内6か所に設置されている県の農林水産事務所では、担当職員が地域を巡回し、直接、農業者などに対して技術や経営方法についての指導を行うなど、農業や農村の振興に向けた多面的な活動を展開しています。
また、新規就農希望者に対して、就農に関連する情報の提供、研修先の紹介、就農計画の作成指導、制度資金の活用に向けた相談などに応じています。
就農した後も、講座や個別の指導を通じ、また、地元の農協や先進的な農家などと連携しながら、新規就農者の農業経営が早期に軌道に乗るよう支援活動を行っています。
⑤農業協同組合(農協、JA)
市町村には農協やその支所があり、農業経営や農村で生活する上で、重要な役割を果たしており、大部分の農家が組合員として加入しています。
農協には、農業全般についての事業をする総合農協と作物(家畜等)別の専門農協があります。
農業者の大部分が加入しているのは総合農協で、通常農協という場合はこの総合農協を言います。
農協は、組合員を相手に農業資材・生活物資の販売、農畜産物の集荷・販売、営農・生活資金の貸出し、貯金の引受け、生命共済、営農指導など組合員の営農・生活全般に関わる幅広い業務を行っています。
また、特に各種制度資金を借り入れる場合は、農協が主な窓口となっています。制度資金では賄えない営農資金なども農協が貸してくれます。
⑥農業経営士、青年農業士
農業経営士とは、地域農業のリーダーとして指導的役割を果たしてもらうため、県が認定している農業者(おおむね40歳以上)です。
農業経営士は、新規就農者等の研修を積極的に受け入れ、いわゆる農業における里親として担い手育成に関する助言指導などのサポートをする役割を担っています。
また、青年農業士とは、地域農業における若きリーダー役として農業経営士らと連携して地域の若手農業者の指導者として活動してもらうため、県が認定している農業者(25歳~45歳)です。
いずれも新規就農者のよき師匠と成り得る心強い味方です。積極的に相談し、地域との関係を築いていきましょう。