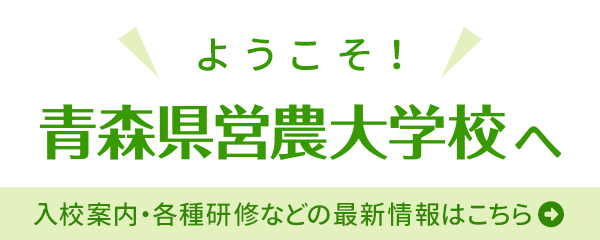掲載日:2024年12月09日

山田俊さん・園実さん鶴田町 / 就農4年目
- 経営概要(栽培品目)
- ぶどう80a(スチューベン)
- 就農前の職業
- 会社員、鶴田町地域おこし協力隊
山田俊さんは岐阜県、園実さんは東京都(八丈島)出身。大都市圏で会社員として生活していたが、農業に興味を抱いていたこともあり、2018年に青森県鶴田町の地域おこし協力隊員として同町に移住。任期中にぶどう栽培の技術や知識を学び、満了後に町内の園地を継承して就農。園地では観光ぶどう園事業も運営している。
就農した経緯
俊さん:大阪・東京で10年ほどサラリーマン生活を送ってきましたが、勤務環境の変化が激しく、家族と過ごす時間もとりづらい仕事に身を置く中で、今後も働き続けられるのか不安を感じていました。
そこで元々興味のあった農業、できれば果樹農家になりたいと考え、果物産地への移住を検討していました。情報収集のため、都内の「ふるさと回帰支援センター」を訪れたところ、青森県鶴田町で地域おこし協力隊を募集していることを知りました。
青森県は、妻の母の実家があり、夫婦で夏祭りに訪れたこともあるなど縁があった土地。鶴田町は、スチューベンの生産量が日本一の産地ということも条件に合ったため、将来的な就農を念頭に、協力隊に応募しました。

就農準備・就農後について
どのようなサポートを受けましたか
俊さん:鶴田町が協力隊として募集していた業務は情報発信でしたが、町に就農の意向を伝えたことで、ぶどう農家として独り立ちできるよう道筋を作ってくれました。
町では、就農希望の協力隊員へ指導をしてくれる農家さんを紹介してくれました。1年目は先輩生産者の「師匠」に栽培技術や知識を学び、2年目からは自分たちで実践。協力隊の任期があるので実際に就農できるのは満了後でしたが、その間は、師匠が園地の管理を引き受けてくれたため、就農時に園地を購入することができました。
支援制度としては、国の「農業次世代人材投資事業(※現:経営開始資金)」や協力隊の起業支援補助金、県の補助事業を、経営が安定するまでの生活資金や観光ぶどう園の資材購入等に活用しました。
栽培技術の習得はどのように行いましたか
園実さん:師匠に教わったほか、県主催の新規就農者研修会や、町内の生産者で作る津軽ぶどう協会の勉強会などで技術や知識を学びました。
近隣で先駆的にぶどう栽培していた若手生産者にコンタクトを取り、アドバイスをもらうこともありました。熟練者と若手では考え方に違うところもあり、それぞれのいいとこ取りをして自分たちの経営に生かしています。

農地の確保について
俊さん:実際に農地が確保できるかは、鶴田町に移住した際に一番気がかりだったことです。
1年目はなかなか見つからず焦っていたのですが、2年目にぶどう園地を手放したいという相談が町に寄せられたことをきっかけに、第三者継承の形で運よく入手することができました。農地が確保できたことは偶然でしたが、日頃から、町などの関係機関に相談していたからだと思っています。
第三者継承とは
後継者がいないためにリタイアする農業者の栽培技術や販路、ブランドといった無形資産と、農地や機械施設などの有形資産を、家族以外の人に一体的に引き継いでいくもので、新規就農者が新たに農業経営を開始する手法の一つ。
資金や機械等の確保について
俊さん:継承した園地は、前年までぶどうを栽培していたため状態が良く、ぶどう樹や支柱など、栽培に必要なものは一式そろっていました。支柱を用意するとなるとそれだけで数百万円は掛かりますし、なによりその年からすぐに収穫できる環境だったのが助かりました。
農薬を散布する際の動力噴霧器などは、師匠や近隣の生産者さんが貸してくれたり、乗用草刈り機は中古品を購入したので初期投資を最小限に抑えることができました。
一方で住まいには困りました。
選果、梱包などの作業スペースに加え、乗用草刈り機やスピードスプレーヤーが置けるような用地のある一軒家がなかなか見つかりませんでした。
中古物件はそれなりにありましたが、住むにはまずリフォームが必要。それなら建てたほうがいいという話にもなりましたが、就農して間もないため融資も受けられず、現実的ではありませんでした。
運よく2年目に条件が整った現在の住家を入手できましたが、それまでは家の一室をつぶして作業スペースに充てるなど苦労しました。


生産物の販路と販路開拓の方法について
園実さん:就農して間もなくのころは全量を市場に卸していましたが、現在は全体の3割ほどは別な販路に乗せています。協力隊員時代から運用していたSNSアカウントを介して友人や知人から個人注文が入り、それが口コミで広がっていっています。
ジュースに加工してもらい、「道の駅あるじゃ」と「道の駅もりたアーストップ」に卸しているほか、鶴田町のふるさと納税の返礼品に登録し、県外からの注文も入り始めました。また、県事業の一環で香港の見本市への出品にもつながりました。
知り合いのりんご農家を参考にして、複数の販路を開拓し、リスク分散をしています。今後はECサイトを使った販売もできればと考えています。
地域や地域農業との関わりについて
俊さん:鶴田町で受け入れる協力隊員は自分たちが初めてだったので、「よそ者」が移り住んでくることを地元のみなさんにどう思われるか心配でしたが、ウェルカムな人たちが多く、生活の節々で応援してもらいました。
協力隊員として地域に入り込むことができた価値は大きく、就農後もいろいろな情報をもらう機会があります。今の住家も、町の情報が集まるとよく言われる床屋さんから「そろそろ売りに出されそう」という話を教えてもらって入手できました。
園実さん:受け継いだ園地では、町内で「はちみつぶどう」と言われるぶどう(一説ではブラックオリンピア)がありました。
脱粒が起きやすく一般向けに出荷できないことから現在は作り手がほとんどいなくなってしまったようですが、味わいが良く、鶴田町ならではの品種だと思うので、できる限り残していきたいと栽培しています。

就農後の生活について
俊さん:就農してからは時間を自分で管理できるようになりました。
サラリーマン時代は朝7時に家を出て、満員電車に1時間揺られて通勤、家に帰ると夜10時という生活で、ストレスもありました。現在は繁忙期こそ朝は早いですが、園地までは自転車で行き、昼食をとりに家にも戻れます。
家族との時間がゆったりとれるようになり、移住してからは家族が4人になりました。美しい岩木山を眺めつつ、好きなラジオを聞きながら作業ができる。本当に農家になってよかったと思いますね。
山田さん夫婦の一日
農繁期

農閑期

年間スケジュール
表は横にスクロールできます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選果、箱詰め (少雪時は剪定も) |
全休 | 全休 (下旬から剪定) |
支柱の補修 枝の結束作業 |
芽かき 間引き |
芽かき、間引き(上旬まで)、誘引 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摘心1回目、房づくり、枝管理 | 摘心2回目 | 収穫 | 選果、箱詰め(少雪時は剪定も) | ||
農業のやりがいについて
俊さん:自分が工夫したことに対し、ちゃんと成果が返ってくることがやりがいですね。
ぶどうは水気を嫌う作物。当初、園地には水はけが悪い箇所があって、そこでの実の出来はやはりよくなかったんです。そこでいろんな農家さんに聞いたところ溝を掘るといいと助言をもらいまして、すごい重労働でしたがスコップで1列を掘ってみました。
そうすると年ごとに良いぶどうがどんどんできるようになったんです。サラリーマン時代はみんなで一つのものを作るという仕事が多かったのですが、自力でやったことの成果が直に返ってくるのは面白いと思います。
園実さん:ぶどうが成り始めるとハサミで切って形を整える「房づくり」をするのですが、「去年は小さめの房が多かったから、今年はもうちょっと大きくなればいいな」と思って作り方を変えたことがあって、そうしたら本当に大きい房ばかりになったんです。
毎年買ってくださる人も「今年は大きいね!」と気付いてくれて、そこでみんなが知らないぶどう栽培の作業や楽しさについて身をもって伝えられたことは嬉しかったです。


青森県及び青森県の農業について、感じること
園実さん:青森では案外、どんな作物でも作れるんだな、と思いました。県外の人たちにとって青森といえば、やっぱり「りんご」。ぶどうを作っていると言うだけでも驚かれますが、青森でも様々な果物を作ることができるし、なんでも美味しい。それは実際に住むまでは知りませんでした。
一方で、農家の高齢化がすごいですね。後継者不足からか、毎年どこかしらで果樹が切られていて、そうしたところを見るのは悲しいです。現在は鶴田町がスチューベン生産では日本一で、地域の売りにもなっていますが、それも頑張って守っていかなければ、そのうち変わってしまうと思います。
俊さん:地域のぶどう農家でいえば、平均年齢が高くなってきていて、ベテランとぼくたち中堅との間の30~50代が少なく感じています。将来、上の層がいなくなった場合、どうなってしまうかという心配はあります。
これからの農業を共に支えていく担い手が増えてほしいですね。
今後の目標について
俊さん:人を雇ってまで栽培面積を広げたいという思いはなく、現在の栽培面積で収益性を高めていく経営ができればと思っています。
以前、東京に売りに行った際には1房350円で安いと驚かれたのですが、青森では150円くらいで売られているんです。販売方法を工夫することで商品価値は高めていけそうです。高付加価値化のため、加工品の開発にも今以上に取り組んでいければとも考えています。
園実さん:スチューベンの認知度を高めることに少しでも貢献できたらと思います。
現在、鶴田町に協力隊員が3組いて就農を目指しており、新しく農業を始めてみようという人は増えてきています。そのうちの1組が自分たちのところで研修中で、今後も受け入れていきたいです。自分たちも同じように教わってきたので恩返ししていきたいですね。

新規就農を目指す方へのアドバイス・メッセージ
園実さん:自分たちもそうでしたが、良い農地がなかなか見つからないという悩みをよく聞きます。
新規就農した人にはあまり話が回ってこないものですが、農家になって2、3年くらいすると情報がすごい集まるようになりました。地元の農家さんから農地を任せてもいいと思われないと話がこないんだと思います。初めはそこまで農地が見つからなくても焦らず何年かやっていると、ちゃんと見てくれている農家仲間から自然と話を持ち掛けられるはずです。
俊さん:ゼロの状態で移住して新規就農しようしても、周りに知り合いもいなく、行政との関係性を築くことも難しいと思います。
その点、地域おこし協力隊は3年の期間で地域の関係づくりができるので、就農に関して有効な制度だと思っています。こういう就農のやり方もあるということは知ってほしいです。

就農に関する詳しい情報はこちらをご覧ください
就農までのステップ就農支援制度
相談窓口一覧
現在募集中の地域おこし協力隊(青森県移住・交流ポータルサイト「青森暮らし」)
先輩インタビュー

加納 良介さん・可奈恵さん
南部町 / さつまいも・じゃがいも・にんにく・とうもろこし

株式会社NAMIKIデーリィファーム
野辺地町 / 生乳・仔牛

葛西 貴大さん
田舎館村 / 冬春いちご(とちおとめ)

株式会社 甲田ファー夢
代表取締役 甲田 秀行さん
十和田市 / キャベツ,ながいも,にんにく

山田 俊さん・園実さん
鶴田町 / ぶどう(スチューベン)

有限会社 まごころ農場
代表取締役 斎藤 靖彦さん
弘前市 / ミニトマト,りんご,農産加工

有限会社 風丸農場
代表取締役 木村 農也さん
鯵ヶ沢町 / 水稲,大豆,りんご

田邊 真太郎さん
平内町 / お米,そば,大豆,野菜(ピーマン他、多品目栽培)

「攻めの農林水産業賞」受賞者たちの今を動画で御紹介します

株式会社中里青果
五戸町 / ながいも、だいこん、ごぼう

みらいファーム・ラボ 株式会社小栗山農園
弘前市 / りんご

農業生産法人 株式会社よしだや
三戸町 / にんにく

沢森 靖史さん
田子町 / にんにく, えごま

高井 啓さん・美奈子さん
平川市 / ミニトマト, ネギ

木村 恵莉子さん
青森市 / りんご

佐々木 基さん
十和田市 / 黒毛和牛, 短角牛

濱田 裕子さん
東通村 / いちご, ほうれん草, さつまいも, そば